今宵は避暑地気分を愉しめる映画 をご紹介します。
映画 をこよなく愛する素人のおしゃべりです。
皆様がひとつでも観たい映画 が見つかれば嬉しいかぎりです。
「五線譜のラブレター」 ヴェネチアの閑雅なひととき
監督:アーウィン・ウィンクラー
脚本:ジェイ・コックス
〈Story〉
作曲家のコール・ポーターは大天使ガブリエル演出による自身の半生が、ミュージカル形式で想起される。
1920年代のパリ社交界で「最も美しい女性」と讃えられたリンダ・リー・トーマスが見初めた男性がコール・ポーターだった。
リンダは彼の音楽や人間性そしてバイセクシュアリティさえも受け入れ、彼の夢を実現させるため共に人生を歩む。リンダはコールに愛されている自覚があり、コールの婚外恋愛を容認する。
結婚している間、コールの仕事はとてもうまくいく。流産したリンダを励ますため、2人はハリウッドに転居する。
コールの浮気は大胆になり、ナイトクラブで男性と抱き合っている所を写真に撮られ、大金を要求される。我慢できなくなったリンダはコールを置いてパリに戻る。
そしてコールは乗馬中に重症を負う。

「五線譜のラブレター(2004)」の主人公コール・ポーターは有名な作曲家です。スタンダードナンバーの昔の作曲家なので、キネ娘さんとサポさんは知らないかな。
コール・ポーターって誰? みたいな感じですよね。
聞くと分かると思います。jazzのスタンダードの「# Night and Day」とかね。
「ジョー・ブラックをよろしく(1998)」の豪華な誕生日パーティーの盛り上がる場面で楽団が最初に演奏していたのが「# Anything Goes!」。その作曲がコール・ポーターです。ミュージカルの作曲家。
「五線譜のラブレター」はコールの半生をミュージカル仕立てで振り返る映画です。年のいったコールと大天使ガブリエルが劇場の客席から演出家のように舞台を見ていると、ステージで半生が演じられます。
「俺の若いときはあんなんじゃなかった」
と喋っている。
コール・ポーターのミュージカルの代表作「# Anything Goes!」から派手に始まります。
ステージが映画の実写に変わって、コール・ポーターとリンダが出会うシーンになる。
1920年代のパリに芸術家がいっぱい集まっています。ピカソやヘミングウェイ、画家や音楽家、日本から藤田嗣治とかね。パリに世界中の芸術家が集まる時代ですね。
パーティー会場でコールがピアノを弾いて遊んでいる。コールを演じるケビン・クラインは歌が上手じゃないんですよ。実はコールも上手じゃなかったという話ですけどね。
リンダ(アシュレイ・ジャッド)は当時のパリでは、離婚した中では一番綺麗っていう噂の女性です。
そしてコールが見初める。二人の気が合って、すぐに結婚するかと思ったら、
「それぞれ独立した関係で暮らしましょう」
リンダはシングルを望んでいてもコールを支える。
二人はヴェネチアに行くんですよ。
それがいいシーンでね、運河の前に建っているホテルでコールが作曲の仕事をしている。運河を船で通るとコールのピアノの音が聴こえる。すぐに作曲ができるわけじゃなくて、試行錯誤していると、リンダはある人を内緒で呼び寄せる。
それがアービング・バーリン。「# ホワイトクリスマス」の作曲家。親しくなって刺激を受けて作曲が捗るんです。イタリアではバレエを中心にしたミュージカルを成功させるんです。実はコールは同性愛者で、女性も好きだし男性も好き、それは付き合う前からリンダに言っていた。
コールはバレエダンサーの男の人と恋仲になっていく。それもリンダは分かっていて、咎め立てもせず、そういうことかと。
「パリを離れて、ニューヨークに行きましょう」
ニューヨークでミュージカルを成功させようという話になる。リンダとコールは改めて結婚する。結婚式の直前に別れた旦那さんが来てコールが同性愛者だと告げる。
「あなたからは暴力しかもらってない。コールからは芸術をもらっている。あなたとは違う」。
リンダが自分で追い払うんです。
強いんですね。
しばらくして二人が食事会に呼ばれる。
リンダがピアノで「# True Love」を弾きながら友達の連れてきたちっちゃい女の子とデュエットをする。それをコールが見ていて、僕たちの子供を作ろうという話になるんですね。
1930年代のニューヨークで、ミュージカル「陽気な離婚」を大成功させる。フレッド・アステアが「# Night and Day」を歌って大ヒットします。
この映画ではフレッド・アステアではなくて、ジャックという人が主演という設定。「# Night and Day」の歌の演出をコールがする。メロディーに入る前のバース(歌い出しの部分)が高音なんです。メロディーに入って低音になって、サビで高音になって、転調してさらに高音になる。ジャックは
「こんな歌は歌われへん」
他の演出家が茶々を入れて
「フレッド・アステアに歌わせろ」
当時は作曲家が歌唱を指導する。作曲から舞台の初日まで関わっていくのが当時のやり方みたいでした。
「セリフを言う気持ちになって、歌えばいいんだよ」。
コールが口ずさんでジャックが合わせてみたら、歌えるようになって3日後に大成功する。
オープニングにリンダが来ないんです。初日はいつもリンダと一緒に舞台を観るんだけど来ない。
実はリンダはその時、流産していたことが後でわかる。
コールが演出家に男性を紹介されて、羽目を外して写真を撮られた時に初めてリンダが説教をするんです。
「パリにいた時は慎み深くて、我慢ができたけども、ここまで羽目を外されたら駄目。言わなかった私が悪かった。一度、離れましょう」。
リンダはパリに戻っちゃう。コールは作曲も上手くいかなくて、リンダからの連絡を待っているけど、電話はかかってこない。
あるとき乗馬をしている時に、落馬して脚を痛めて入院する。片足を切断しないといけないほどの大怪我。そこでリンダが戻ってきてくれるんです。
義足ではピアノのペダルが踏めない。
作曲が思い通りにいかない状態が数年続いて、さらにリンダが病気になって苦難の時間が続きます。
映画の仕事をするようになる。今までの成功した舞台を映画化していく。
病気になったリンダが
「私は神の手に委ねられて、ショービジネスはコールの手に委ねられる」
とコールを励ます。リンダは自分の命がいよいよと分かって
「少し早いけど、お別れを言わせてほしい」。
リンダの枕元でコールは「# So in Love」を歌う。あまり上手じゃない。
そこは忠実ですね。
映画の中でケビン・クラインがちょっと歌うと、舞台で歌手が歌うシーンに繋がる。作曲の時もピアノを弾きながらケビン・クラインが歌うと舞台のシーンになってダイアナ・クラークが歌ったり。
最後はナタリー・コールが歌ったりするんです。ナット・キング・コールの娘さんです。有名な歌手もふんだんに出てきます。
「# Anything Goes!」で始まって、「# Anything Goes!」で終わる。
ミュージカルって、ミュージカルパートで話が進むことが多くて1曲を歌っている間に二人が恋に落ちる。そういうミュージカル映画を説明するのは難しいですね。
正式にはミュージカル映画じゃないのかも。作曲シーンや上演シーンで歌う。曲の選び方は物語に沿っている。
ただね、「# ビギン・ザ・ビギン」という歌があるんです。これはアップテンポでメジャーな明るい曲なんですね。この映画の中ではリンダの流産の後の悲しいシーンにマイナーコードで使われる。
アレンジされている。
そのマイナーの方がオリジナルの可能性もある?
ビギン(Beguine)ていうダンスがあるんですよ。ビギンのダンスを始めましょうという歌が「#ビギン・ザ・ビギン(Begin the Beguine)」です。だから曲の内容も明るいんですけどね。
ダンスの歌。
そうそう、ダンス踊ろうみたいな。
「# Night and Day」はハマっていたけどね。
「昼も夜もまたあなたのことを思って心が苦しい。これを解消するには一緒になるしかない」
結婚する場面にピタッとはまる。
「五線譜のラブレター」っていうタイトルは、リンダに向けて愛の歌を作るから。
コールが
「全ての曲は、君のために作ったんだ」
と言うとリンダが
「一部はそうだったね」。
現実的ですよね。
リンダは大人ですね。自立していて強いんですね。
アシュレイ・ジャッドがいいんですよ。
でもフレッド・アステア役は登場しなかった。
利用の許可が下りないとか。
フレッド・アステアは「タワーリング・インフェルノ(1974)」が最後の映画出演だったんですよ。年寄りだけどダンディーな役でした。
タップダンスではナンバーワン。フレッド・アステアの活躍は1930年から50年代ぐらい。モノクロの映画が多いですね。当時はカット編集しないんですよ。カメラが大きいのでドーンと置いてワンカットで1曲を踊る。
へえ。
練習でもリハでも本番でもステップ位置が一緒というのがフレッド・アステアです。
すごいですね。
小道具も使って帽子掛けを相手にダンスしたり(「恋愛準決勝戦(1951)」)、傘を畳んで投げて遠くの傘立ての中にずばっと入れるとこまでをワンカットで踊ったり(「パリの恋人(1957)」)。
初めの頃はジンジャー・ロジャースとペアで映画に出ていたんです。ロジャースが羽をいっぱい付けたドレスで踊ったことがあるんですよ(「トップ・ハット(1935)」)。踊ると羽が落ちてしまうんですよ。羽根を踏むとツルツル滑る。それでもフレッド・アステアのステップは変わらない。
Eくん
年間 120本以上を劇場で鑑賞する豪傑。「ジュラシック・ワールド」とポール・バーホーヘン監督「ロボコップ(1987)」で映画に目覚める。期待の若者。
サポさん
「ボヘミアン・ラプソディ」は10回以上鑑賞。そして、「ドラゴン×マッハ!」もお気に入り。主に洋画とアジアアクション映画に照準を合わせて、今日もシネマを巡る。
キネ娘さん
卒業論文のために映画の観客について研究したことも。ハートフルな作品からホラーまで守備範囲が広い。グレーテスト・シネマ・ウーマンである。
検分役
映画と映画音楽マニア。所有サントラは2000タイトルまで数えたが、以後更新中。洋画は『ブルーベルベット』(86)を劇場で10回。邦画は『ひとくず』(19)を劇場で80回。好きな映画はとことん追う。
夕暮係
小3の年に「黒ひげ大旋風(1968)」で劇場デビュー。開演に照明が消え気分が悪くなり退場。初鑑賞は約3分。忘却名人。
検分役の音楽噺 ♫
映画音楽好きとしては、今回『五線譜のラブレター』が取り上げられたのは嬉しいです。
クラシック音楽の作曲家の伝記映画は幾つかありますが、ポピュラー音楽の作曲家がテーマというのは珍しいのではないでしょうか。
なんてエラそうなことを書いていますが、かく言う僕がコール・ポーターの存在を知ったのは、84年の『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』が最初。
ケイト・キャプショー演じるヒロイン、ウィリーが上海のナイトクラブで唄うオープニング・ナンバーが「エニシング・ゴーズ」。
当時は全体のスコアを担当したジョン・ウィリアムズが作曲したのだと思い、ウィリアムズ凄いや!なんて思っていましたが(笑)、
それがコール・ポーターによるスタンダード・ナンバーだと後で知って愕然としたわけです。
『五線譜のラブレター』でもオープニングを飾るナンバーとして流れてきますね。
もっとも、それ以前に映画音楽以外で既にコール・ポーターのナンバーに触れていたのが、
スペインのシンガー、フリオ・イグレシアスによる日本でも大ヒットした81年のナンバー「ビギン・ザ・ビギン」。
たしか、当時テレ朝系の「題名のない音楽会」で、司会の故・黛敏郎さんが、
「フリオのナンバーは最初から最後までメジャーコードだが、原曲は途中でマイナーに転調する」
なんてことを語っておられたのをおぼえていましたが、作曲したコール・ポーターの名前まではおぼえてなかったのです。
『五線譜のラブレター』ではシェリル・クロウがずっとマイナーコードで唄っています。
さらにいえば、同じくテレ朝系の「日曜洋画劇場」。
淀川長治さんの「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」の後に番組最後に流れるナンバー。
あれを聴くと毎週、ああ日曜日ももう終わりか・・・と一抹の寂しさを感じましたが、
あの曲こそコール・ポーターによるミュージカル『キス・ミー・ケイト』の中のナンバー「ソー・イン・ラヴ」だったんですね。
『五線譜のラブレター』でもクライマックスのじつにドラマティックなシークエンスで流れてきます。
というように、コール・ポーターのナンバーって、無意識のうちに刷り込まれていたような印象があります。
『五線譜のラブレター』、いい映画なんですが、文中で触れられているように、かつては配信で鑑賞できたのですが、
現在はなぜか配信されていません。鑑賞するにはDVDを借りるか買うかしか方法がないのは残念。
また、豪華アーティストがコール・ポーターのナンバーをカヴァーしたサントラも名盤ですが既に廃盤。
あ、サントラマニアの僕の家には当然、ありますよ(笑)


「プロヴァンスの休日」 南フランスのやわらかな陽の光
監督・脚本:ローズ・ボッシュ
〈Story〉
シングルマザーで求職中の母親はカナダでインターンシップを受けることとなる。
長男アドリアン、長女レア、聴覚障害のある次男テオは、プロヴァンス地方の祖父ポール、祖母イレーネのもとで夏季休暇を過ごすことになる。
母親エミリーは実家から家出し17年間疎遠となっている。
祖母のイレーネはポールに告げずに、孫を受け入れるつもりでいた。
ポールは皮肉ばかりで早くも障壁が生じる。

「プロヴァンスの休日」は主演がジャン・レノ。
パリに住んでいる三人の子供たちが、母親エミリーが海外に行くので、夏の間おじいちゃんとおばあちゃんの家に預けられるストーリー。
ティーンエイジャーの男の子アドリアンと女の子レアとまだ小さな男の子テオ、上の二人は現代っ子で田舎には行きたくない。末っ子のテオは聴覚障害で喋ることができない。おばあちゃんのイレーネ(アンナ・ガリエナ)が迎えに来てくれる。おじいちゃんのポール(ジャン・レノ)は気難しくて昔エミリーが家を出てから疎遠になっていたので受け入れにくい。イレーネは優しく迎え入れてくれる。
子供たちは料理が口に合わなくて
「こんなん食べられへん」
パソコンでゲームしようとして
「電波が入らない」
文句ばっかり。
イレーネは2ヶ月ぐらい一緒に過ごすから仲良くしてほしいと思い、地元のお祭りに上の二人を連れて行く。ポールがテオと一緒にいることになって畑仕事を一緒にする。ポールは手話ができないので、ジェスチャーで
「こうやったらいいんやで」
って仕事をさせる。
「よくやった」
テオはポールに褒めてもらえて打ち解けていく。そこからポールは上の二人とも気持ちが通じていく。
レアに好きな人ができる。ピザ屋をしている人。
プロヴァンスはフランスの田舎ですけど、のどかでみんなが畑仕事をしていたり、地元の人が集まる酒場があったり、みんながギュッと繋がっているコミュニティなので、噂がすぐ広がるんですよ。
ポールが街の人たちと飲んでいる時に、レアの相手がドラッグの売人やと聞く。
レアは「二人で旅行に行きます」と書き置きを残して出ていってしまう。
ポールとイレーネが昔ヒッピー生活をしていて、その時のツーリング仲間がプロヴァンスに会いに来て一緒にバイクでレアを探しに行ってくれる。アドリアンも後からついてきている。アドリアンもポールと打ち解けて家族になっている。
レアが見つかるとドラッグでぐったりしている。レアだけを連れ帰って医者に診せる。
レアはポールが助けに来てくれると思わなかった。
ポールは彼氏がドラッグの売人だとはレアに教えなかった。
そうして休暇が終わります。
ポールは名残を惜しむ子供たちをパリに連れ戻す。母親エミリーが空港で出迎えてポールと再会します。気まずそうなエミリーにポールが
「また遊びに来たらいい」。
空港で話す二人の背景がすごい速さで動いて立ち話の長さが伝わります。それがラスト。ハートフルな映画です。プロヴァンスの乾燥している夏の景色。砂と太陽の夏。
ゴッホがいそうな景色。
からっとした夏ですけど、いい景色だなあって。
他にもいろいろな出来事があるんですよ。アドリアンも好きな女の人ができて、その人がアイス屋さんで大量のアイスを買うとか、ポールがオリーブの品評会で優勝するとか。
オリーブを育てている。
その話も急に始まるんです。お知らせが来てイレーネが
「おじいちゃん優勝したわ」
ポールが何十年もかけてチャレンジして、やっと優勝できた。堅物ポールの嬉しそうな笑顔でほんわかする。
二人の兄妹は食べ物屋さんに弱いんやね。
好きになった相手も姉弟。
レアがそれを知らずに弟といる彼女を見ちゃって、
「お兄ちゃん、あの人に彼氏がいたわ」
レアも失恋したと二人で落ち込んでたら、姉弟と分かって
「よっしゃ」
みたいな。
反対されてないのに駆け落ちをしたの?
ポールは反対していて、最終的にという感じ。それまでにもお祭りで、二人でいるところをポールが見て、
「何してるんや」
って、手を上げそうになって、耐えきれなくなってレアが出ていく。
レアは都会っ子で自然派、地元の野菜しか食べない。自分を持っているタイプだけど恋愛経験がなかった。
ジャン・レノはぴったりな感じ。
周りと打ち解けない堅物系が多いイメージ。
「レオン(1995)」の面影がある。
最後のシーンで、ぐっときそう。
父娘が打ち解けます。エミリー(ラファエル・アゴゲ)は最近離婚したシングルマザー。
おじいちゃんとおばあちゃんが複雑な気持ちで重かったんやろね。
明るくて寄り添ってくれるおばあちゃんでよかった。
キャラクターがジャン・レノとバランスが取れている。
ポールとイレーネがヒッピーだった。いろんなところを転々として最後にプロヴァンスで落ち着いた。
ヒッピーは70年代に世界中で流行っていた。
アメリカのイメージがありました。すごく長い道路を走る。
ポールは「イージー・ライダー(1970)」に憧れていたのかな。
おばあちゃんが見せる写真がロン毛で分かりやすい。
オノ・ヨーコみたいな感じですね。
孫にうるさく言っても、若いときはあるわけやからね。
ある人の名前が出るとポールは暗くなるんですね。それは亡くなったポールの弟で、イレーネが昔好きだった。子供たちはポールの心に触れて打ち解けていく。
日本映画で作れそうですね。
家族の話は作りやすいですね。
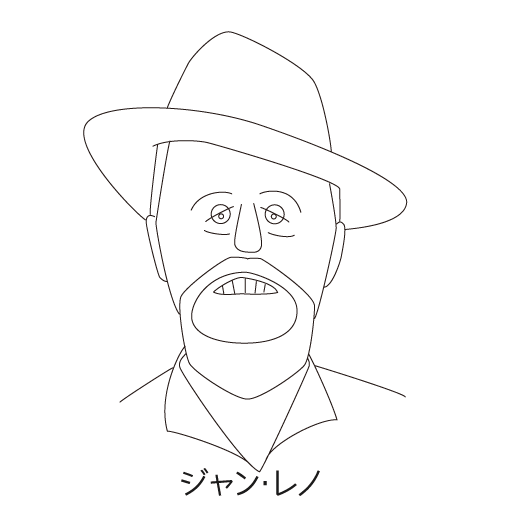
「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」 大ルーブル宮殿に密かに眠る絵画とは
監督:渡辺一貴
脚本:小林靖子
原作:荒木飛呂彦
〈Story〉
岸辺露伴は骨董店を取材し、オークションに出品されるフランスの画家モリス・ルグラン作の黒い絵に興味を抱く。落札したものの競売相手に絵を強奪される。
絵は手元に戻るが、その絵の裏にはモリスがフランス語で「これはルーヴルで見た黒。後悔」と記していた。
また、露伴は青年期に出会った女性奈々瀬のことを思いだす。露伴の祖母が運営する下宿に暮らしていた奈々瀬は、露伴の漫画に興味を示し「この世で最も黒く、邪悪な絵」の存在を教える。露伴は奈々瀬に惹かれ、彼女をモデルとして漫画に描くが、奈々瀬はその絵を切り裂き、露伴に詫びて姿を消す。
露伴は「最も黒い絵」がルーヴル美術館にあることを思いだし、ルーヴル美術館へ取材に行く決意をする。
ルーヴルを訪ねた露伴は、問題の絵が、作品が保管されていないはずのZ-13倉庫にあると知らされる。美術館関係者も把握していない事態に、露伴は通訳のエマ・野口や東洋美術のキュレーター・辰巳隆之介、消防士たちを伴う条件で絵の見学を許される。
一行はZ-13倉庫で、ヨハネス・フェルメールの作とみられる絵画を発見する。
辰巳はその絵を贋作と断言するが、露伴は真作であると見抜き、ある推理を披露する。

「岸辺露伴 ルーヴルへ行く(2023)」は漫画が原作だから話しにくいな。
あれって単発の作品ですか?
NHKのドラマシリーズが好評だったので映画化されました。
元々は「ジョジョの奇妙な冒険」に出てくる脇役の漫画家です。そのキャラクターが人気でその8話目の最後に、
「今度海外に取材に行きましょう」。
そこから、映画ではルーヴル美術館に行く。
ルーヴルが映るんですか?
ちゃんとルーヴルに行っています(原作はルーヴル美術館のバンド・デシネ・プロジェクトで荒木飛呂彦が依頼された作品だった)。映画は岸辺露伴(高橋一生)が青年時代の時に聞いた「この世で最も黒い絵」という邪悪な絵をふと思い出して、ルーブル美術館に所蔵されていると知って取材に行く。
露伴がギフトという能力を持っている。意図した人間を本の状態にして、その人の人生を読むことができるんですよ。その能力が発動された人は、そのことに気づかず、気絶し、本のページに書き込まれた行動をしてしまう。
何でもできる。
自分にも書き込むことができるから、フランス語が話せるって書いたら、話せるようになる。ルーブルではフランス語で会話ができているんですよ。
これからの未来が本になるの?
本人の今までに起きてきたことの記憶が本になっている。
過去の行間に書き込むと、過去が変わる?
そうじゃないです。書き込むページはどこでもいいんです。何々の記憶を忘れると書いたら、どのページに書いてもその記憶を忘れる。書き込まれた文字が消えたら、また記憶が戻っちゃう。露伴がピンチに陥るたびにその術で切り抜けるのが面白い。
探している黒い絵が露伴の青年時代に魅かれていた女性・奈々瀬(木村文乃)との思い出に繋がっています。昔おばあちゃんの家に仮住まいしていた時に下宿していた人。離婚したばかりのミステリアスな女性で、その人がいきなり部屋に誘って黒い絵の話をしてくれる。
その数日後に奈々瀬が突然いなくなってしまう。
露伴は漫画家としてデビューしてから何年もそのことを忘れていたけど、ふと思い出す。黒い絵を研究するために美術オークションで似た黒い絵を買って帰り道にそれを盗まれる。なんでやろうと、その買い取った黒い絵について調べていくとルーブル美術館に繋がる。
お話はミステリーっぽい
ミステリーですね。露伴はファンタジー。
敵は出てこないんですか?
黒い絵が敵。人が触れてはいけない怪異。
毎回そういう設定?
主人公が漫画家でその能力があるのは全シリーズ一貫しています。毎回不思議な体験があって露伴が自ら首を突っ込んでいって話が展開されます。
経験のためにやるんですね。漫画のネタとか。
岸辺露伴シリーズのドラマも面白いし、映画だけ観ても楽しいです。

「怪物」 何層にも組まれた物語
監督:是枝裕和
脚本:坂元裕二
〈Story〉
ある街で雑居ビルに火の手があがる。シングルマザーの麦野沙織と息子湊が消火活動を自宅から眺めている。
湊が沙織に「豚の脳を移植した人間は?人間?豚?」と問う。その後、息子の身の回りで不審な出来事が相次ぐ。
沙織は息子がいじめや教師からの暴力を受けていると疑い小学校へ通い詰める。担任である保利や校長に問いただすがまともな話にならない。他の教員から、校長が最近孫を事故で亡くしたことを知らされる。
保利は湊が星川依里(より)をいじめているかもと疑念を抱き、星川宅を訪ねると依里の父親から「あれは化け物。豚の脳が入っている」と告げられる。

最近映画は観られました?
「怪物(2023)」を観たよ。
私も観に行きました。
映画らしい映画を久しぶりに観た気がしました。でも怖くなかったですか。ホラー映画を観ているぐらい怖かったんですよ。ドキドキしながら観ましたね。
僕はミステリーっぽかったかな、実はこうだった、実はこうだったと仕込みが何層もある。
事の真相がどんどん明かされていく。
そんな風に語られるから観ている方は、先入観を持って観ている自分たちが怪物なのかなと自分の先入観を意識しちゃう。
犯人探しをしちゃいますもんね。
誰が悪いんやろみたいな目で見ちゃいます。
何度もひっくり返される。
目線が変わるんですよ。親の目線から子供の目線になると全然違って見えて、こんなことがあったんやって。
手法としては昔からある。
アケフセのタイミングが上手い。
最後は解釈がわかれそうな感じでしたね。
アケフセが何度もあるけども、最後はアケがないけど、きっとまたフセられていると。。。
そこは、自分の推測をしてしまうところ。先入観と裏の読み合いですね。
坂元裕二さんがカンヌ国際映画祭で脚本賞を獲ったのは間違いなかったね。


(対話月日:2023年6月23日)